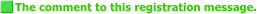本日は
バイコンインプラントの導入セミナーに参加してきた。
バイコンインプラントは日本のシェアはあまりないスペシャルな
インプラントである。私が最も興味をもったのではノーセメント・ノースクリュー構造ということでセメントの取り残しの問題やスクリューの緩みを考える必要がないということからである。
インプラントのほとんど99%はセメントもしくはスクリュー構造体のどちらかをかならず使用しなければシステムがなりたたない。
アンキロスインプラントで難しいのはセメントの取り残しが出てしまうことである。特別な
インプラントは使い方を間違えると悪い方へいくがうまくつかいこなすととてもいい。両刃の剣である。
さて、
バイコンインプラントには画像のような手榴弾のような団子虫のようなスペシャル
インプラントがある。この
インプラントは下顎の臼歯部の骨の高さが極端にないケースでは大変有効であろう。
歯茎の貫通部は直径2.0㎜のものと3㎜のものが存在する。私なら貫通部が3㎜のものを大臼歯部に使いたい。高さは5㎜、5.7㎜、6㎜がある。
こんなスペシャルなシステムはここだけである。
他には前歯のケースで貫通部が2㎜のものをつかえば相当に審美的に有利であることは誰でもわかる。
構造や考え方は
アンキロスインプラントに共通する部分がある。フィンの部分が咬合圧を分散する点も同じ。歯肉貫通部が細いのも同じである。このような形態の
インプラントは一度骨の中に完全に植立ができればそう簡単に感染することはないと思う。
短い
インプラントといえばノーベルのショーティーを思い出すがあれは必ず1スレッド吸収するのでいずれは問題がでることだろう。
インプラントとアバットメントの連結が甘いからマイクロスレッドにバクテリアが繁殖して骨の吸収が進む。
バイコンや
アンキロスが骨の吸収がすくないのはモーステーパーの角度が浅いからだ。
バイコンはわずかに1.5度
アンキロスは5.8度、アストラテック12度、
ストローマンのボーンレベルが15度となっていて6度を超えると
インプラントとアバットメントは緩みやすくなる。緩むからねじで締めなければいけないということになる。
バイコンは軽くたたくだけでしっかりと回転もせずに勘合する。
アンキロスは15Nでいいのはテーパー角度が浅いからである。
インプラントとアバットメントが緩まず緊密に勘合していればバクテリアは繁殖せずに周囲の骨は安定化する。
この構造をよくわかってない先生がノーベルを使うと思う。まあそれでも悪いなりに弱点を知りながらつかえばいいと思う。
治療方針
簡易サイト
症例
マウスピース矯正
求人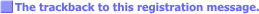 -- この記事への外部リンク:
-- この記事への外部リンク:
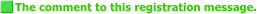

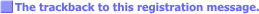 -- この記事への外部リンク:
-- この記事への外部リンク: